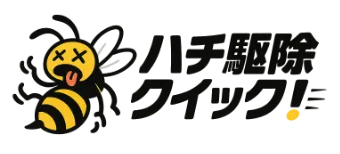蜂の巣を実物や写真、映像などで見て「これは何で出来てるのか?」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
日本には、4,000種類以上の蜂が生息していると言われており、その中でよく知られているのがミツバチ、アシナガバチ、スズメバチですが、それぞれ巣の素材や形状・構造は異なります。
そんな蜂の巣が「何で出来ているの?」と疑問に思ったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の記事では、「蜂の巣は何で出来てるのか」という疑問をお持ちの方に向けて、蜂の種類別に主な素材や構造を解説し、使われなくなった巣がどうなるのかも紹介します。
蜂の巣が何で出来てるのかを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも蜂の巣とは?
昆虫は、基本的に個体で活動するものが多いのですが、中には社会性昆虫と言われる集団で生活する種類も存在し、蜂や蟻はその代表例です。
蜂の巣は、蜂が集団生活を送り、繁殖や育児をおこなうために作る住処です。巣の中には女王蜂・働き蜂・幼虫が生活しており、それぞれが役割を果たして巣を維持しています。
巣の中にはたくさんの穴があり、そこに卵を産み付け、幼虫を育てたり、食料を貯蔵したりします。
なお、巣穴は六角形になっており、「隙間なく敷き詰められる」「強度が高い」「材料の節約になる」といった、構造上もっとも合理的な形になっています。蜂は進化の過程でこの形にたどり着き、より効率的で安全な巣作りをおこなえるようになったと考えられています。
これは、「ハニカム構造」と呼ばれていて、飛行機の翼のパネルや建築材料などにも使われています。
蜂の巣は何で出来てる?素材・構造など
それではここから、今回のテーマである「蜂の巣は何で出来てるのか」を、ミツバチ、アシナガバチ、スズメバチに分けて紹介します。
ミツバチ

主に「蜜蝋(みつろう)」という物質で作られています。蜜蝋は、働き蜂のお腹にある「ロウ腺」から分泌されるもので、ミツバチはそれを口でこねて巣を作っていきます。
ミツバチは花の蜜を集めて「蜂蜜」を作り、それを食料としています。蜜蝋と蜂蜜は作られる仕組みが異なりますが、蜜蝋の分泌には十分な栄養が必要で、花の蜜も蜜蝋の生産にとって大切な存在なのです。
なお、1匹のミツバチが1gの蜜蝋を生成するためには、約8g以上の花の蜜が必要とも言われています。
巣の見た目は、平らな板が何枚も垂れ下がったような形で、表面に六角形の巣穴があり、その中に卵を産み、幼虫を育て、蜂蜜を貯蔵しています。ミツバチは、他の種類の蜂と異なり、働き蜂も女王蜂と一緒に巣の中で冬を越すため、蓄えた蜂蜜は冬の大切な食料となります。
アシナガバチ

巣穴が外から見えて、シャワーヘッドのような形が特徴なのが、アシナガバチの巣になります。
アシナガバチの巣は、巣の全体を保護するための外壁、卵を産みつけ幼虫を育成するための巣穴、巣の強度を保つための支柱で構成されており、アシナガバチが嚙み砕いた木や竹の繊維、植物の茎などに唾液を混ぜて作った、紙のような素材でできています。
巣材には、繊維がからまりやすく、乾くとしっかりと固まる性質のあるセルロース繊維がたくさん含まれている木の内側の部分が使われるため、軽量ながら強度にも優れています。
巣の作り始めは、女王蜂が一匹でおこない、育房ができるとそこに卵を産み、また育房を増やして卵を産むという活動を繰り返し、同時に幼虫の世話もおこないます。基本的に一つの育房に一つの卵が産みつけられます。
スズメバチ

スズメバチは、木の樹皮や朽ち木を咬み砕いたものを唾液と混ぜたものを薄く延ばして巣を作ります。外皮で覆われ、ボール状になっていくため、内側が見えないようになっていますが、初期の段階では育房がある平らの板のような巣盤から作られます。働き蜂が増えると、巣盤を下方向に追加し、それに合わせて外側を覆っていくように巣が作られます。
そのため、内部の構造は円の中に巣盤が直線的に並び、、3層~5層程度から、大型の巣を作る種類では10層以上にもなっている場合があります。
基本的に出入りするための穴は一か所で、大きさは一定ではなく、活発に活動する日中は大きく、巣に戻って休む夜間は小さくなります。その際、見張りの働き蜂が外をうかがって警戒しています。
使われなくなった蜂の巣はどうなる?

ここまで、蜂の巣が何で出来てるのかを、蜂の種類ごとに解説しました。では、使われなくなった蜂の巣はどうなるのでしょうか。
アシナガバチやスズメバチは、その年に新しく誕生した女王蜂が冬眠して次の春を迎えることになりますが、基本的に旧女王蜂や働き蜂は冬までには死滅してしまい、蜂の巣は空っぽになり、翌年に古い巣が再利用されることはありません。
そのため、古い蜂の巣は風雨や劣化により自然に崩れ落ちていきますが、蜂の排泄物や死骸が残っていることがあり、それらが腐敗して悪臭やカビの原因になることがあります。また、他の害虫が住み着くこともあります。
一方で、ミツバチは新しい女王蜂が誕生すると古い女王蜂は一部の働き蜂を連れて他の場所で巣を作り、冬の間も働き蜂と一緒に巣の中で冬を越します。そのため、再利用されることが多いのですが、蜜蝋が劣化してきた場合などは、その巣を捨てて新しい巣を作ります。その場合、ミツバチの巣は栄養価が高いため、害虫や害獣を引き寄せることがあります。
例えば、蜜蝋蛾という蛾は、蜜蝋を栄養源としていて、巣に卵を産み、幼虫が巣を食い荒らします。ネズミなどの害獣も蜜蝋の甘いにおいに引き寄せられることがあります。
蜂の巣の素材・構造について
蜂の巣の素材や構造は、種類ごとに異なり、それぞれに特徴があり、放置するリスクもあります。特にミツバチの巣は蜜蝋で作られており栄養価が高く、甘いにおいが残るので、放置すると害虫や害獣が寄り付く原因になります。また、アシナガバチやスズメバチの巣も木の繊維からできているとはいえ、蜂の排泄物や死骸が腐敗して、カビや悪臭が発生したり、害虫の住処になることもあります。
そうした理由から、「蜂がいないから大丈夫」と蜂の巣を放置するのはリスクがあります。
また、駆除後の蜂の巣の放置は戻り蜂の原因になり、女王蜂が生き残っていた場合には、再利用してまた産卵をする可能性があります。
もし、自宅の庭や軒下などに「蜂の巣がある」という場合には、「ハチ駆除クイック」へご相談ください。
ハチ駆除クイックは全国対応の蜂駆除業者で、過去10年間で10万件以上駆除した実績がございます。
蜂の種類や巣の大きさによる料金変動はなく、作業完了後に見積もり時にご提示した金額から追加料金をいただくことは一切ございません。作業内容や料金にご納得いただいてから作業に入らせていただき、相見積もりも歓迎です。
電話だけでなく、メールやLINEでの無料相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル:0120-996-974(電話受付時間8時〜22時)
メール:365日24時間受付